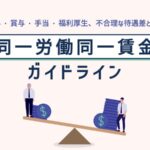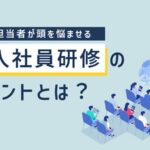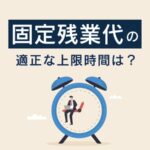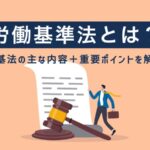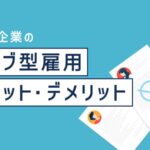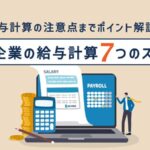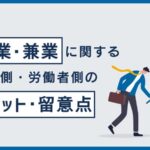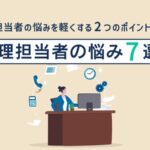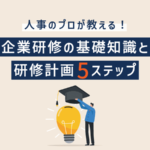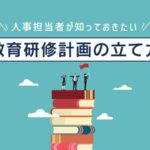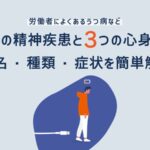-

-
働きながら年金受給!在職老齢年金とは?老齢基礎年金・老齢厚生年金も分かりやすく簡単解説!
2024/6/25 加給年金, 厚生年金, 受給開始年齢, 国民年金, 在職定時改定, 在職老齢年金, 基本月額, 報酬比例部分, 支給調整, 総報酬月額相当額, 老齢厚生年金, 老齢基礎年金, 適用事業所, 障害等級1級もしくは2級
「年金を受給する人」と言われると、多くの人は定年又は定年再雇用後に働かなくなった人が受給する老齢年金をイメージすると思います。 「老齢により退職した人の生活保障のために支給する」というのが本来の目的な ...
-

-
65歳以上の複数就業者が加入できる雇用保険マルチジョブホルダー制度|マルチ高年齢被保険者とは?2022年1月施行
2024/6/18 2以上事業所, ハローワーク, マルチジョブホルダー制度, マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届(マルチ喪失届), マルチ喪失届, マルチ雇入届, マルチ高年齢被保険者, 資格取得手続き, 資格喪失手続き, 雇用保険, 雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書
2022年(令和3年)1月から、複数の事業所で短時間勤務する65歳以上の就労者が、一定の条件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」と言います)となることができる雇用保 ...
-

-
通勤時の交通事故も労災保険が適用!任意保険との調整・休業特別給付金との調整はどうなる?
2024/6/11 交通事故証明書, 任意保険, 任意保険基準, 休業損害, 休業補償給付, 労働者災害保険法第12条の4, 労災保険療養給付, 対人賠償保険, 慰謝料, 損害賠償請求権, 支給調整, 業務災害, 民法709条, 求償, 治療費, 特別休業給付, 第三者行為災害届, 自動車損害賠償保険, 自由診療, 自賠責, 自賠責基準, 通勤災害, 過失割合, 過失相殺
通勤や業務中に交通事故に遭い、治療や休業が必要となった場合は、自動車保険から補償を受けると思われがちですが、労災保険を併用することも可能で、利用する人が増えていると言われています。 そこで、今回は障害 ...
-

-
同一労働同一賃金ガイドライン|給与・賞与・手当・福利厚生、不合理な待遇差とは?
2024/6/4 不利益変更, 不合理な待遇差の解消, 労使間の合意形成, 単身赴任手当, 同一労働同一賃金ガイドライン, 地域手当, 安全衛生, 役職手当, 手当, 時間外労働に対して支給される手当, 有期雇用労働者, 深夜労働又は休日労働に対して支給される手当, 特殊作業手当, 特殊勤務手当, 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針, 短時間労働者, 福利厚生, 精皆勤手当, 給与, 賞与, 通勤手当及び出張旅費, 通常の労働者, 食事手当
2021年(令和3年)4月1日より、中小企業を含めすべての企業に適用された「同一労働同一賃金」のルール。 同一労働同一賃金とは、「雇用形態にかかわらず、同じ仕事をする労働者は同じ賃金を得る」という意味 ...
-

-
人事担当者が頭を悩ませる新入社員研修のポイントとは?
日本では多くの大企業において、新入社員の採用後、配属前の新入社員研修を行います。 履歴書で篩にかけられ、面接を切り抜けてきた新人たちだけに、会社としては役に立つ人材と見込んでの採用ですが、どこに配属す ...
-

-
固定残業代の適正な上限時間は?企業の固定残業メリット・デメリット+適正な固定残業代3つの要件とは?
2024/5/21 36協定, 固定残業代, 固定残業代のデメリット, 固定残業代のメリット, 固定残業代のリスク, 対価性, 所定時間外労働, 明確区分性, 法定休日労働, 法定時間外労働, 深夜労働, 精算条項, 適正な固定残業代3つの要件
固定残業代とは、残業の有無に関係なく、一定時間分の残業をしたものとみなし、割増賃金として定額で支給される賃金です。残業代が毎月固定で支払われるため「残業ありきの制度」という印象があり、近年、求職者から ...
-

-
リファラル採用を始める前に要チェック!企業のメリット・デメリット+トラブル事例とは?
2024/5/14 インセンティブ, デメリット, トラブル事例, メリット, リファラル採用, 人間関係の悪化, 似た性質の人材, 大量採用, 対処法, 志望動機, 採用コスト, 短期採用, 自社に合った人材
人材確保が難しくなっている近年、各企業では優秀な人材を低コストで獲得するために、様々なアプローチが行われています。 その中でも、コストを抑えつつも、自社に合った人材を獲得できることで注目を集めている手 ...
-

-
労災保険(労働者災害補償保険)とは?業務災害・通勤災害・第三者行為災害を分かりやすく解説!
労働者のいざというときのための保険給付である労災保険ですが、どのような災害に対応している保険かご存知でしょうか? 労災保険とは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して、 ...
-

-
厚生年金保険とは?適用事業所、被保険者要件、保険料、保険給付の種類などをチェック!
2024/4/30 70歳未満の者, パートタイマー・アルバイト, 任意適用事業所, 厚生年金保険, 厚生年金保険料, 外国籍の者, 強制適用事業所, 日本年金機構, 標準報酬月額, 標準賞与額, 老齢厚生年金, 被保険者, 試用期間中の者, 遺族厚生年金, 障害厚生年金
「厚生年金保険」は、「労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」を目的として定められた公的年金制度のひとつです。 今回は、企業に勤め ...
-

-
労働基準法とは?労基法の主な内容+重要ポイントを解説!就業規則・法定三帳簿も要チェック!2024年4月法改正対応
私達が仕事をする上では、多くの法律が関係してきます。 その業界特有の法律もありますが、経営者を始め人事労務担当者がまず知っておかなければならないのは労働関係の法律です。特に労働基準法は最 ...
-

-
中小企業のジョブ型雇用|メリット・デメリット・ジョブ型雇用導入のポイントとは?
2024/4/16 ジョブ・ディスクリプション, メンバーシップ型雇用, 上司の評価力, 人事評価制度の再構築, 人材定着率の低下, 同一労働同一賃金, 業務の煩雑化, 業務内容の明確な定義付け, 組織の生産性向上, 職務記述書, 長時間労働の防止
ジョブ型雇用とは、業務内容を明確にした上で人材の採用・評価等を行う制度です。 同一労働同一賃金の実施や新型コロナウイルスの流行等を背景に、近年特に注目を集めています。実際に、ジョブ型雇用の導入を検討し ...
-

-
人材育成の一環である教育研修の基礎知識
企業が保有している資産の中には物やお金、情報などがありますが、最も重要な資産とされているのが「人」です。社内の「人」が育てば競争力をアップさせることができ、会社の利益を最大化することも可能になるのです ...
-

-
中小企業の給与計算7つのステップ~給与計算の注意点までポイント解説! 新任人事労務担当者必見!
人事と労務が分担されていないことが多い中小企業での給与計算は、人事労務業務の中でも大部分を占める業務です。勤怠管理から給与計算、給与支払まで、担当者として責任をもって業務を完了させなければなりません。 ...
-

-
国民年金・厚生年金等の年金の種類|老齢年金、障害年金、遺族年金とは?日本の公的年金制度を分かりやすく簡単に解説!
2024/3/26 公的年金, 公的年金2階建て構造, 公的年金制度, 共済年金, 厚生年金, 国民年金, 年金, 社会保障制度, 第1号被保険者, 第2号被保険者, 第3号被保険者, 老齢厚生年金, 老齢基礎年金, 老齢年金, 遺族厚生年金, 遺族基礎年金, 遺族年金, 障害厚生年金, 障害基礎年金, 障害年金
日本の「公的年金制度」は、社会全体で高齢者を支えるために整備された仕組みで、日本に住む20歳から60歳未満のすべての人に加入する義務があります。 徐々に支給開始年齢が引き上げられ、将来年金を受け取るこ ...
-

-
労働基準法|年次有給休暇とは?正社員、アルバイト、パートの有給休暇付与日数をチェック!
2024/3/19 一斉付与方式, 不利益取り扱いの禁止, 交代付与方式, 個人別付与方式, 半日単位・時間単位の年次有給休暇, 年次有給休暇, 年次有給休暇の時効, 時季変更権, 有給休暇付与日数, 計画的付与
急速に進む少子高齢化といった経済社会の構造変化や国際競争の激化、また、長引く経済の低迷は、これまでの右肩上がりの経済や市場の成長を前提にしてきた企業経営を大きく変化させており、より高度な経営が求められ ...
-

-
副業・兼業に関する企業側・労働者側のメリット・留意点とは?裁判例も簡単解説|副業・兼業の促進に関するガイドライン
2024/3/12 スキルアップ, マンナ運輸事件, 健康管理, 兼業, 副業, 労働基準法, 労働時間, 労働者から副業・兼業の申し出, 十分な収入の確保, 十和田運輸事件, 安全配慮義務, 就業時間の把握, 東京都私立大学教授事件, 自分がやりたい仕事, 資格の活用
労働者の働き方に関するニーズのうち、副業・兼業を希望する労働者は年々増加傾向にあり、「自分がやりたい仕事」「スキルアップ」「資格の活用」「十分な収入の確保」など、理由は様々です。 一方で、企業において ...
-

-
中小企業よくある経理担当者の悩み7選!経理担当者の悩みを軽くする2つのポイントとは?
経営資源のひとつである「カネ」と密接に関わることから、経理担当者には多くの業務が発生します。 そのため、日常的に悩みを抱えており「他の経理担当者はどのような内容に悩んでいるのだろう」と気になる中小企業 ...
-

-
フレックスタイム制|時間外労働・コアタイム・労使協定・清算期間・残業上限規制をスッキリ解説!
2024/2/27 36協定, コアタイム, フレキシブルタイム, フレックスタイム制, 上限3ヵ月, 働き方改革関連法, 労使協定, 所定労働時間, 時間外労働, 標準となる1日の労働時間, 残業上限時間規制, 法定労働時間, 法定労働時間総枠, 清算期間, 清算期間上限3ヵ月, 総労働時間, 過不足賃金
昨今、働き方改革により多様な働き方を選択できるよう様々な法改正が行われています。そんな中2019年、より柔軟な働き方の選択を可能とするため「働き方改革関連法」によりフレックスタイム制の労働時間の清算期 ...
-

-
【完全保存版】人事のプロが教える!今さら聞けない企業研修の基礎知識と研修計画5ステップ
2024/2/20 Off the Job Training, Off-JT, OJT, On-The-Job Training, Self Development, インハウス研修, ハラスメント, 人事, 人材育成, 人材開発, 他流試合, 企業研修, 労務, 基礎知識, 外部研修, 教育研修, 研修, 社内研修, 社員研修, 社外研修, 組織開発, 職場外教育, 職場教育, 自己啓発, 野外研修, 集合研修
この記事では、経営者や人事・教育研修担当者、事業責任者が必ず押さえておくべき企業研修(他には、法人研修、社員研修、集合研修と呼ばれたりもします。)を始める際のポイントや、基本的な情報を分かりやすく説明 ...
-

-
人事担当者が知っておきたい教育研修計画の立て方
2024/2/13 OJT, On-The-Job Training, 中堅研修, 人事担当者, 人材育成, 企業研修, 教育研修, 教育研修計画, 次世代幹部, 次世代経営者, 研修, 社員研修, 管理職研修, 若手研修, 階層別研修
経営戦略に欠かせない人材育成は、将来的に労働人口が減少していく日本において、重要かつ喫緊の課題です。 人件費を考慮し、正社員を減らしてパートやアルバイトを増やしてきた企業では、正社員に期待する要素が増 ...
-

-
要チェック!中小企業が気を付けるべき中途採用面接の見極めポイント6選
企業の人事業務って、身近なようで実は意外と知られていないことも多いのではないでしょうか? 経営の三大要素「ヒト・モノ・カネ」で最も優先順位が高い「ヒト」を扱う人事労務業務は、企業にとってとても重要な役 ...
-

-
労働者によくあるうつ病など7つの精神疾患と3つの心身症の病名・種類・症状を簡単解説
2024/1/30 うつ, うつ病, パーソナリティ障害, パニック障害, メンタルヘルス, メンタルヘルス疾患, 不安障害, 休職, 双極性障害, 復職, 心身症, 摂食障害, 早期治療, 早期発見, 精神疾患, 統合失調症, 緊張型頭痛, 過敏性腸症候群, 適応障害
企業のメンタルヘルス対策の一環として、どのようなメンタルヘルス疾患やストレス疾患があるかなどについて、事前に確認しておくことは大切なことです。 今回は、労働者によくみられるうつ病などの精神疾患や心身症 ...
-

-
管理職に求められるマネジメントスキル3つのポイント
管理職になる前と後では、仕事で求められる能力が異なってきます。そこで重要になってくるのがマネジメントスキル。 マネジメントスキルとは、簡単に言うと「目標達成のために組織をまとめ上げる力」のことです。マ ...
-

-
ハラスメント|企業が講ずべき職場におけるセクハラ・マタハラ(妊娠・出産)防止対策+事例
2024/1/16 セクシュアルハラスメント, セクハラ, マタニティハラスメント, マタハラ, 事例, 制度等の利用への嫌がらせ型, 妊娠・出産等に関するハラスメント, 対価型セクシュアルハラスメント, 性別役割分担意識, 性的指向, 性自認, 状態への嫌がらせ型, 環境型セクシュアルハラスメント
職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメントなどのハラスメント防止対策は、労働者が企業で安心して能力を発揮しながら働き続けるために必要な対策です。 また、企業にとってもハラス ...